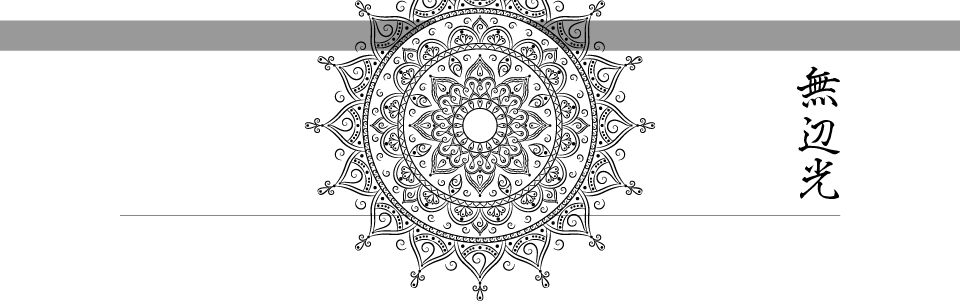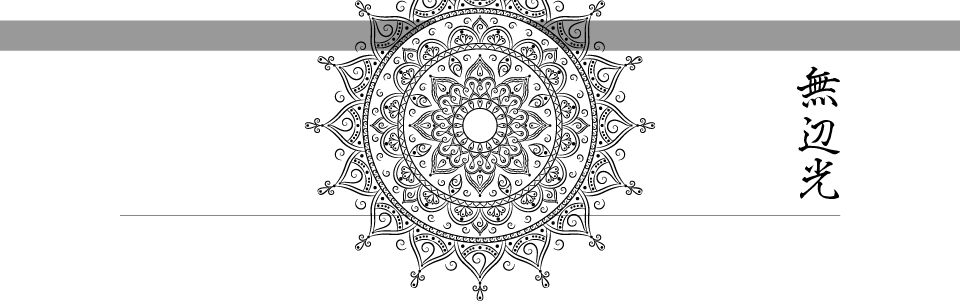大和物語
百四十五
昔、平城の帝に仕う奉る采女ありけり。顔容貌甚じう清らにて、人々よばひ、殿上人などもよばひけれど、逢はざりけり。其の逢はぬ心は、帝を限なく目出たき者になん思ひ奉りける。帝召してけり。扨後又も召さゞりければ、限なく心憂しと思ひけり。夜昼心に懸りて覚え給ひつゝ、恋しく佗しく覚え給ひけり。帝召しゝかど、事とも思さず、さすがに常には見え奉る、猶ほ世に経まじき心地しければ、夜密に出でて、猿沢の池に身を投げてけり。斯く投げつとも、帝は得知し召さゞりけるを、事の序ありて、人の奏しければ聞し召してけり。いと甚う哀がり給うて、池の辺に大行幸し給うて、人々に歌詠ませ給ふ。柿本の人丸、
わぎも子がねくたれ髪を猿沢の池の玉藻と見るぞ悲しき
と詠める時に、帝、
猿沢の池も辛しなわぎも子が玉藻潜かば水ぞ乾なまし
と詠み給うける。扨此の池に墓せさせ給うてなん、帰らせ御座しましけるとなん。
百四十六
同じ帝、立田川の紅葉いと面白きを御覧じける日、人丸、
立田川もみぢ葉流る神南備の三室の山に時雨降るらし
帝、
立田川紅葉乱れて流るめり渡らば錦中や絶えなん
とぞ遊ばしたりける。
百四十七
同じ帝、狩いと畏く好み給うけり。陸奥国岩手郡より奉れる御鷹、世に無く賢かりければ、二なう思して御手鷹にし給うけり。名をば岩手となん附け給へりける。其れに彼の道に心ありて、預り仕う奉り給うける大納言に預け給へりける。夜昼之れを預かりて、取飼ひ給ふほどに、如何がし給ひけん、逸し給うてけり。心肝を惑はして覓むるに更に得見出でず。山々に人を遣りつゝ覓めさすれど更に無し。自らも深き山に入りて、惑ひ歩き給へど甲斐も無し。此の事を奏せで暫しも有るべけれど、二日三日にあげず御覧ぜぬ日なし。如何せんとて内裏に参り、御鷹の失せたる由を奏し給ふ時に、帝物も宣はせず、聞し召し付けぬにやあらんとて、又奏し給ふに、面をのみ守らせ給うて、物を宣はず、怠々しと思したるなりけりと、我れにも有らぬ心地して、畏まりて在すかりて、此の御鷹の覓むるに、侍らぬ事如何様にかし侍らん、などか仰事もし給はぬと奏し給ふ時に、帝、
言はで思ふぞ言ふに勝れる
と宣ひけり。斯くのみ宣はせて、他事も宣はざりけり。御心にいと言ふ甲斐なく惜しく思さるゝになんありける。之れをなん世の中の人、本をば左右附けゝる、旧は斯くのみなん有りける。
百四十八
平城の帝位に御座しましける時、嵯峨の帝は坊に御座しまして、詠みて奉り給うける、
皆人の其の香に愛づる藤袴君が御為と手折りつる今日
帝、御返し、
折る人の心に叶ふ藤袴うべ色毎に匂ひたりけり
底本:国立国会図書館デジタルコレクション『校註日本文学叢書 第四巻』物集高見 監修 他