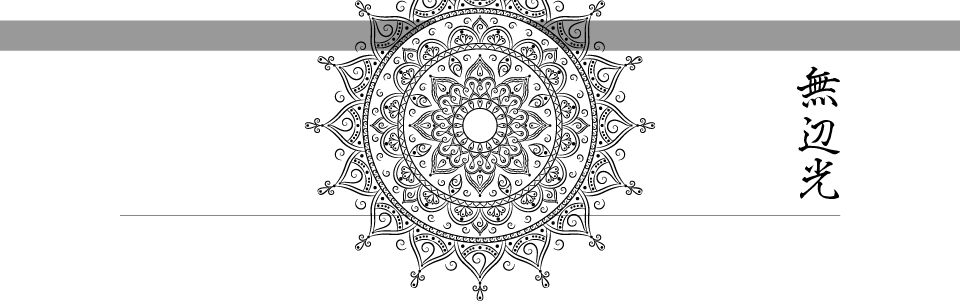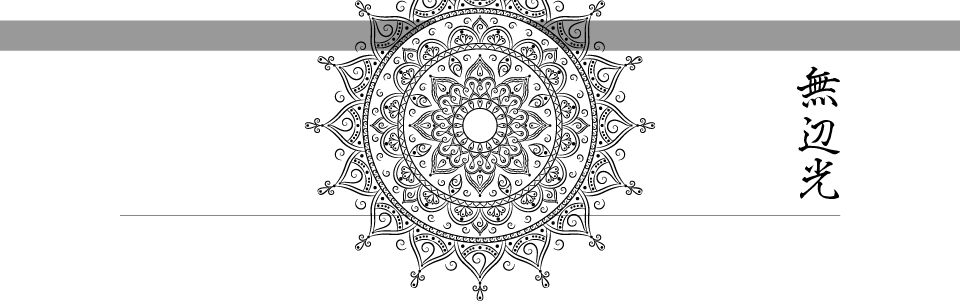それから、この速須佐之男命は、御棲居の御殿を御造りになるべき適当の場所を、出雲国の内に探し求めなさいましたが、須我といふ処においでになりまして、「此地に来たらば、わたくしの気分が清々しくなつた」と仰せられて、やがて此の地に御殿を建てゝ、御住ひなさいますことゝなりました。かやうな訳で、此の地を現今でも須賀と云ふのであります。
此の須佐之男大神が、はじめて須賀の宮殿を御造りになりましたときに、其処から雲が立ち騰りましたので、御歌を御咏みになりました。其の御歌は、
八雲起つ 出雲八重垣 夫妻籠に 八重垣作る 其の八重垣を。
〔雲が起つ、雲が涌き起つ、涌き起つ雲が、作る八重垣、雲の垣、夫婦棲ませうと八重垣作る、作る雲の垣、其の八重垣よ。〕
そこで、彼の足名椎神を御召し出しになりまして、「卿は、わたくしの居る此の宮殿の事を掌る長官と御成りなさい」と仰せられて、其の名号を稲田宮主須賀之八耳神と御附け下さいました。