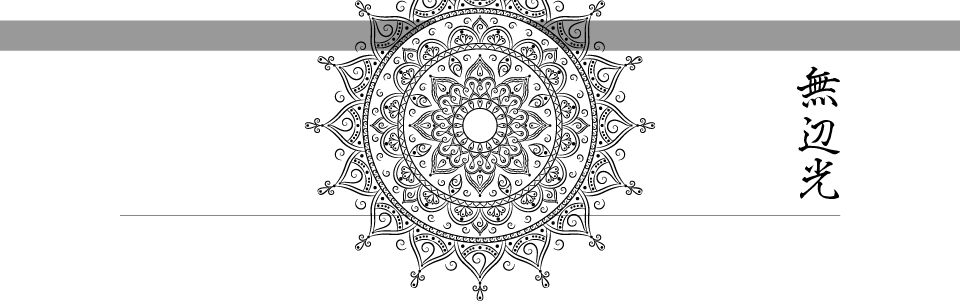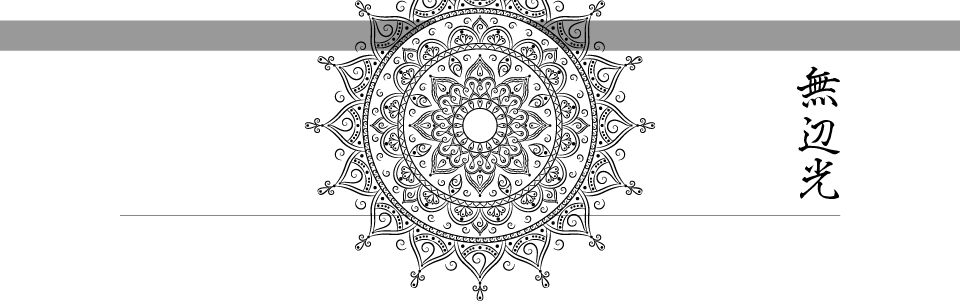〔口訳〕八月十日新院御到着の由、讃岐国からの報が著いた。松山にお出になつたが、国司が直島といふ所に御所を御造営したので、其処へお遷り遊ばした。四方に築垣を築き、門一つ、日に三度の供御を奉る外は、訪ふ人もない淋しい鄙の御住居であつた。
(お淋し気な御様子を原文には次の如く述べてゐる。)
さらでだに習はぬ鄙の御住居はかなしきに、秋もやう〳〵更け行くまゝに、松をはらふ嵐の音、草叢によばる虫の声も心細く、夜の雁の遥かに海を過ぐるも故郷に言伝せまほしく、暁の千鳥の洲崎に騒ぐも、御心をくだく種となる。我身の御嘆よりは、僅かに付奉り給へる女房たちの伏し沈み給ふに、弥々御心ぐるしかりけり。
新院は佗しい配所の御住居に、明け暮れ在りし日の夢を追ひ給ひ、「望郷の鬼とならん。」と仰せられたが、御発念あつて五部の大乗経を三年間かゝつて御写経遊ばされ、貝鐘の音も聞えぬ所に置くのを残念に思召して、八幡山か高野山、御許があるならば鳥羽の安楽寿院の故鳥羽法皇の御墓所へ奉納し度き旨、仁和寺の五の宮へ申入れさせられた。五の宮から関白忠通へ此由お伝へになり、忠通は色々御取計らひ申上げたが勅許なく、御写経を御戻し遊ばされたので、御室から書を添へて御返しになつた。
「御咎が重くて、御手跡たりとも都近くへは置けません。御気の毒に存じますが、何とも致方が御座いません。」
新院は御返事を御覧遊ばされて御無念に思召された。
「残念な事だ。此度の事に就いては自分も悔ひ、悪心懺悔の為に此写経をしたのだ。それに筆跡さへも都に置かない程の取扱ひを受けては仕方がない。此経を魔道に回向して、魔縁となつて遺恨を晴らさう。」
と御恨み遊ばされた。此由が都へ聞えたので、康頼を御使として讃岐へ検分に差遣はされたが、柿の御衣の煤けたのに、長頭巾を召され、大乗経の奥に御血を以て御誓状を認め、千尋の海底に御沈め遊ばされた。其後は御爪もお切り遊ばさず、御髪もそのまゝに、御姿を変へて悪念に沈ませられた。
斯くして八年の間お暮し遊ばされ、長寛二年八月二十六日、御齢四十六歳で志戸といふ所で崩御遊ばされ、白峰といふ所で荼毘に附し奉つた。
新院の御怨念によつてか、御配流の後三年目、平治元年十二月九日、信頼に語らはれて義朝が大乱を起し、三条殿を焼き払ひ、院(後白河院)及び主上(二条天皇)を押し込め奉り信西の一類を亡ぼしてその死骸を掘つて首をさらす様な有様となつた。結果は康頼・義朝共に滅んだが、まことに乙若の言つた様になつた。旃檀は二葉より薫しいと言ふ通り、乙若は幼少ではあつたが武門に生まれ兵の道を心得てゐた。
仁安三年の冬、西行法師が諸国修行の途次、白峰の御陵に参拝して往時を思ひ出でて、一首を詠じた。
よしや君むかしの玉の床とてもかゝらむ後は何にかはせむ
治承元年六月二十九日崇徳天皇と御追号があつた。
本書は共訳者のうち、能勢朝次が担当しました。
底本:
国立国会図書館デジタルコレクション『物語日本文学 第二期 第五巻 保元物語・平治物語』藤村作 等 訳